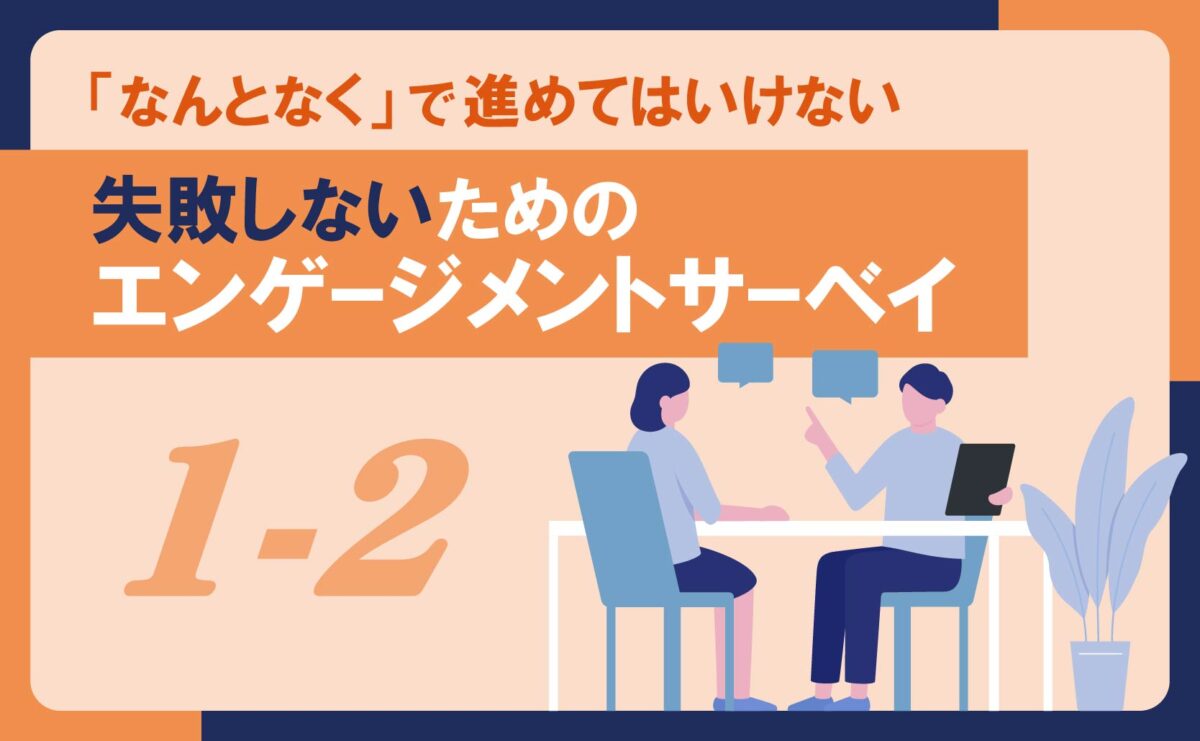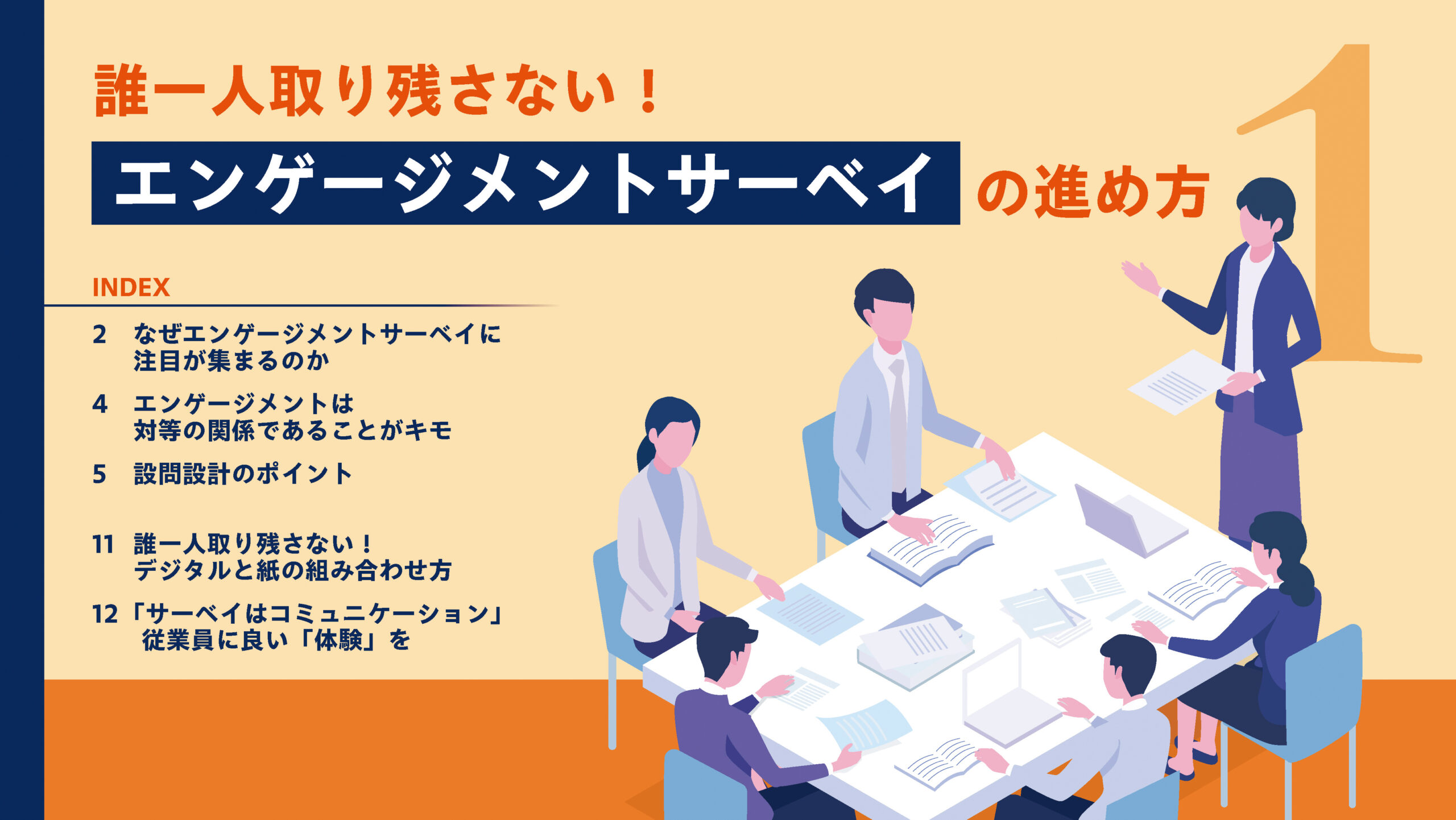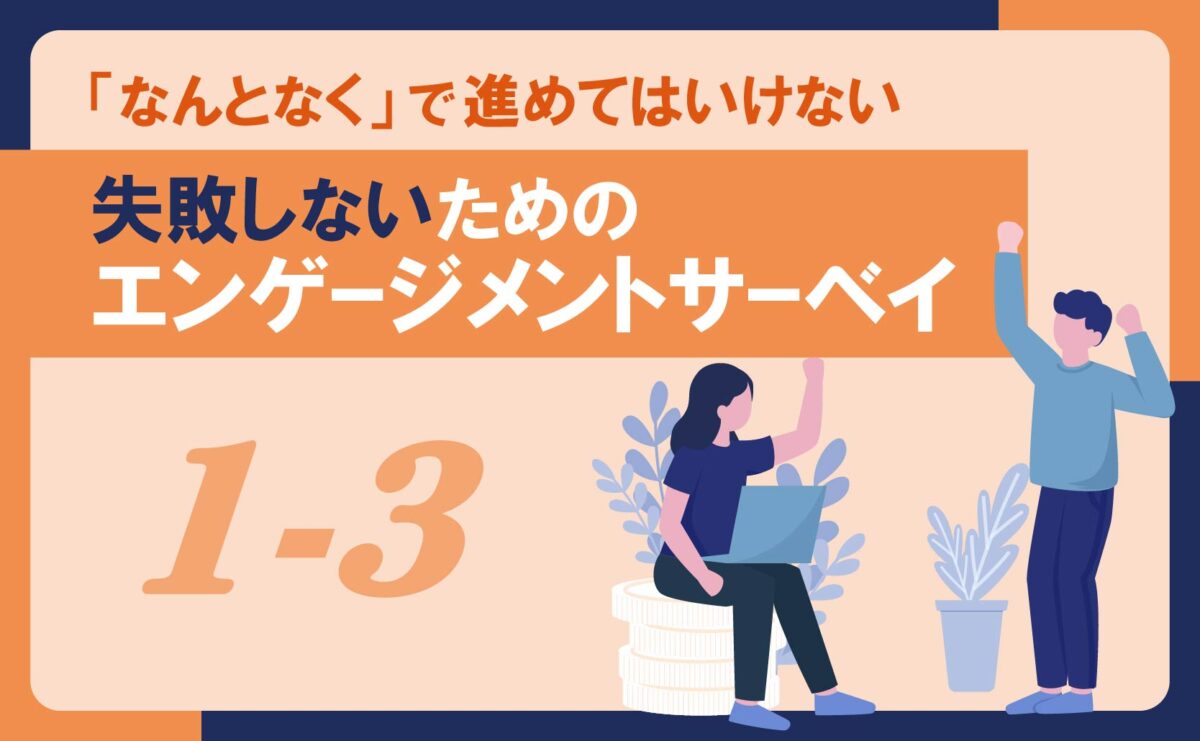質問項目をどうする? 効果的なエンゲージメントサーベイの設問設計の仕方とは?
「サーベイ自体がエンゲージメントの施策である」という前提で考える。
「エンゲージメントとは、会社と個人がWin/Win の関係で結びついていること」
と前回のブログで書きましたが、そのことを忘れてエンゲージメントサーベイの目的や背景を理解せずに質問項目の設計や調査を進めてしまうと、サーベイ自体が従業員のエンゲージメントを下げてしまいかねません。
エンゲージメントサーベイ自体も実はエンゲージメント施策であるという点に気を付けて丁寧に設問を設計したいものです。
実際にエンゲージメントサーベイの質問項目を考える際には、回答者に趣旨や目的の理解を得ることと、答えやすいように設問の順番を考えて設計することが大切です。
また設問は「はい・いいえ」で答える回答が多い選択肢形式で定量的なデータを獲得し、従業員が自由に意見が書ける自由回答形式をバランスよく組み合わせることがポイントになります。
具体的な質問項目の種類や順番については、
\PDF資料「誰一人取り残さない!エンゲージメントサーベイの進め方 」をご覧ください/
ワーディング(表現や言い回し)作成 4つのポイント
エンゲージメントサーベイを設問を作成するうえで、とても重要になってくるのが
設問文や選択肢の表現・言い回しを意味する「ワーディング」です。
このワーディング次第でエンゲージメントサーベイの成否が決まりかねません。
というのも、分かりにくい文章だったり、人によって解釈が分かれてしまう文章だったりでは、調査で正しいデータを取ることができなくなってしまいます。
ワーディングでは、特に以下の4つのポイントを踏まえた上で作成しなければなりません。
- 難しい言葉を使っていないか。(専門用語など)
- あいまいな言葉を使っていないか。
- 誘導的な質問をしていないか。
- ひとつの質問で複数のことを聞いていないか。
例えば②については、「職場の雰囲気はいいと思いますか?」という設問があった時、自分の部署の雰囲気なのか、会社全体の雰囲気なのかがわかりません。
おそらく従業員によって解釈が分かれてしまいそうです。
ほかにも「部門」「グループ」「チーム」のような似たような言葉を用いる際は、それぞれに定義づけが必要になってくることもあり注意が必要です。
ワーディングについては、
\PDF資料「誰一人取り残さない!エンゲージメントサーベイの進め方 」をご覧ください/
中間選択肢「どちらともいえない」を、どう使うか?
中立・中間の選択肢である「どちらともいえない」を入れるべきか外すべきか。
これは本当に悩ましいところです。
選択肢が
| ①そう思う | ②ややそう思う | ③あまりそう思わない | ④そう思わない |
の4段階なら、あいまいさを回避できます。
一方、
| ①そう思う | ②ややそう思う | ③どちらともいえないい | ④あまりそう思わない | ⑤そう思わない |
の5段階であれば、中立的な意見が反映できます。
中間選択肢を入れるケースと入れないケースで、それぞれメリットがありますので、よく踏まえたうえで選択肢をお考え下さい。
中間選択肢を入れるメリット・・・回答者の負担軽減、現実に即した回答、極端化の排除 など
中間選択肢を入れないメリット・・・積極的な意見が引き出せる、結果が明確になる など
抜け漏れが起こってしまう設問設計とは?
経営陣への評価を恐れたり、従業員満足度調査の延長という感覚でエンゲージメントサーベイを行ってしまうと、「会社の将来像」や「経営方針」についての設問設計や質問項目に抜け漏れが生じるという傾向があるようです。
抜け漏れのない設問の設計ポイントについては、
\PDF資料「誰一人取り残さない!エンゲージメントサーベイの進め方 」をご覧ください/
― その②おしまい ―
「エンゲージメントサーベイの効果が今一つだった」
「従業員エンゲージメントを進めようと思っていた」
そんな経営者様や人事採用をご担当の皆様へ。
社員・職員向け調査に20年以上携わってきたプロデューサーが、全従業員の声を“もれなく”集めて、社内の現状を的確に把握するためのコツをまとめました。社内満足度調査やエンゲージメントサーベイを計画する際に参考となる情報です。
お役立ち資料「誰一人取り残さない!エンゲージメントサーベイの進め方vol.1 」
下記から無料でダウンロードできます。
必要事項をご記入の上でお申し込みください。
\資料ダウンロードはこちら/
- こちらの記事も合わせてご覧ください。